こんにちは、夜が涼しくなりましたね。冬が苦手なので急に寒くなるのではとビビるちゃむです。
大好きお醤油。今日は香川県のかめびし醤油✨✨
かめびし醤油さんの特徴


創業1753年(宝暦3年)
国産大豆(非遺伝子組み換え)香川県産の小麦 オーストラリア産の天日塩に
天然にがりを加えた塩。
にがりを使用する事で本来の塩水の塩に近づけています。珍しいです。
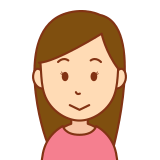
お豆腐を造る時にいれるわね。
私の若かしり頃ににがりダイエットって言うのが流行ったわ。
かめびし醤油の最大の特徴は日本で唯一『むしろ製法』で醤油を造っている蔵元であること。
今は衰退してしまった伝統製法で、唯一今でも造っているのがこの、
かめびし醤油さんです。
なぜ、衰退したのか?
✔ めちゃめちゃ重労働、そして熟練の技も必要。量産も出来ない。
✔ 醤油技術を継承する人も減り機械化が進み衰退。
などが原因。
むしろ製法とは
むしろ:い草や藁などで編んだ敷物(ゴザをイメージしてもらったら)
大豆は蒸す 小麦は炒る 種麹は麹菌を小麦に加えたもの
まず、大豆に小麦と種麹を混ぜたものを
むしろの上に均一に広げます。
大きさは畳1畳ほどの大きさ。
これを、木造の大きな室内で
下段:簀(竹を藁で編みつないだもの)
中段:むしろ
その上に:麹
の順に10〜14段を積み重ねる これを10〜14棚ほど造る。 この工程を盛り込みといいます
次の日(二日目)になっなんと!!!
全てをむしろから落として、全部混ぜ返した後にもう一度むしろに均一に広げます🙀
麹の粒同士が固まってしまうのでほぐす為。
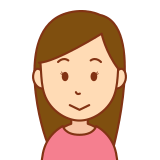
コレは大変!
(3日目)
窓の開閉で温度調節
(4日目)出麹
麹を盛り込み部屋からだして塩水を加えもろみ蔵の桶へ
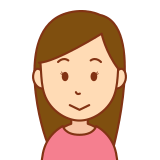
この4日間は寝ずに番をして温度管理をするのよ
*室内は上下段で異なり上段は品温が高くなる傾向が有るためにローテーションなどが必要
麹つくりはもっとも発酵するものにとって大事な工程なのでここでは一切の妥協は許されません。

これは機械に頼りたくなるね
日本酒の工程と良く似ています🍶
この工程を機械でする蔵元さんが増えてきています。
自動通風製麹装置 温度管理もして2日目の切り返しも機械が。
寝ていーんです!!🤤
その他では、むしろを使わずに釘を使っていない、板で出来た麹蓋(約300✕450✕50の浅い木箱)で盛り何段も重ねていきます。
釘を使わない理由:室内はとても湿度が高い為に金属部分に麹が触れると金属の酸化が麹菌の働きの妨げになってしまう為。
工程も大変だけど、衛生管理も大変です!!麹蓋も使用後カビなどの繁殖を抑える為にキレイに拭きとったり(洗うのかなぁ??)乾燥させてと大変だけどむしろはもっと大変そうですよね、、、それも踏まえて機械化なんでしょうね🌝
機械に頼らずにむしろを選ぶ理由
むしろに寝かせることにより水分を調整してくれて適度な湿度を保ってくれる。

個人的な意見だけど、藁やい草で編んでいるので、草の香りも定着すると思う
落ち着く草木の香りが
一、麹
二、櫂
三、火入れ
醤油造りに置いて定石の言葉
麹造りが何よりも重要。ここを機械に任したくない気持ちは大いにわかりますよね。
手造り、人が加わった味って何故かあるんです!機械は完璧なのでしょうが、(怒られるかもですが)人は完璧には出来ないから均一ではない部分とかのムラが複雑性を生み出すと思います。ときには微妙な失敗が驚きの発見になるように、何でも完璧で同じでは駄目だと思うのですよね。
*一個人の意見です*
ずっと変わらずむしろを守ってきたかめびしさんだが、仕込み期間、量の問題などなどで機械を導入を検討し造ったことが有るみたいです。
その結果、今までの味とは別物だったみたいです。
むしろで仕込んだ麹は機械で造った麹とは全く異なり、
生き生きとしています。生き物として愛情をかけて育ててこそ、本来の持ち味が生まれます。
数字には表せないものの、機械には出せない味が確かにあります。
引用元:かめびし
数百年経つ醸造蔵の杉桶で仕込み濃い口醤油では二年 三年 二〇年の歳月をかけている。
約230種類もの独自の酵母菌が住み着いており独自の旨味がゆっくりと引きだされています。
蔵住み酵母の特有の香りと深い味がたまりません!!浅い蔵のお醤油はあっさり?してて良いのは良いのですが、牡蠣とかおひたしなど。自分はこの独特なしっかりとした味が好きです。
牡蠣鍋とかにもぐっと深みが増します。辛くはなく深みとコクは有るけど醤油辛さはないですね。
絶滅しかけている日本の古木良き伝統製法を是非、守り続けて欲しいと個人的に強く思います。
木桶も今は絶滅危機にあり今はたったの1社のみ
素晴らしい日本の文化、醤油を多くの人に知って欲しいと思いつつ
今日はこのへんで
素晴らしい今日をAu revoir


