こんにちは、ちゃむです。
香りだけでもインパクが凄い!お酒がすすむ いや、止まらなくなるお醤油
いしり魚醤
🦑 イカのハラワタとお塩のみで造られた魚醤です。濃厚です 濃厚過ぎます🌝
ちゃむはご飯🍚🍚🍚🍚🍚 🌝
よく、出店とかで売られているイカの丸焼きの様な香りで、イカをギギュンッッって濃縮した旨味成分が半端ないお味です。けれども、タイのナンプラーやしょっつるの様な塩辛さまではいかず、カネイシ醤油さんのいしり魚醤は少しマイルドさがあります。

🦑カネイシ醤油さんのお醤油はじっくりじっくりと時間を掛けて旨味を引き出す為、イカの風味が充分に沁み込んだ芳醇な風味のいしりが出来上がります。
いしり(る)とは
いしるといしりの違いは原料にあるみたいです。
どちらも石川県でつくられている伝統魚醤です。
しかーし能登半島では呼び方が異なり、能登町ではいしりと言うが輪島や門前はいしる、よしると呼ぶみたいよ。
要するに魚醤はいしりともいしるともいい、方言の違いって事かな?!
因みに秋田県はしょっつる(主にハタハタ) 香川県はいかなご醤油があり、いしり(る)は日本三大魚醤の一つです。
お料理に
魚醤は日持ちがいいです。
冷たい料理よりも温かい料理に使うと魚醤の旨味とマイルドさが増すので出来たら温かい料理に掛けて楽しんで下さい🌝
魚醤の歴史
醤油 魚醤 どちらも長い歴史をもつ発酵調味料です。
醤油は大豆、小麦粉、麹、塩で造られます。
魚醤は魚又は魚の内蔵と塩のみで造られる。
魚醤はタイでナンプラー、ベトナムでヌクマムに該当します。
魚を使った調味料は世界中にあるが、アジアがもっとも広く多く使われている。
魚醤は紀元前3〜4世紀から誕生していて、長い歴史を持ちます。
古代ローマで魚や魚の内臓を塩漬けにして発酵させた調味料が使われていた。
魚醤の原型。ガルム
古代中国でも鮒醤と言う魚を発酵して調味料として使われていた。
タンパク質が豊富で日持ちする事から貴重な物でした。
日本で魚の塩漬け発酵が造られていたのは弥生時代頃。
奈良や平安時代には貴族や寺院など階級が上の方を中心に高級調味料として広く使われていた。
これは、醤油も一緒。
16世紀以降は交易によってさらに広く世界で知れ渡る。
現在日本では地方の魚や特徴にあわせた魚醤が多く造られている。主に石川県 秋田県など。
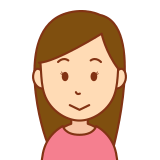
発酵ブームなどで魚醤も大きく注目されるようになったわ
では今日はこのへんで
今日という素晴らしい一日を
Au revoir



《お料理に合わすなら》
🦑 ペペロンチーノ
アンチョビの代わりにいしりをジュワっと火が付いている時か、フライパンがまだ熱い状態の時に鍋縁に
🦑 アヒージョ
アヒージョに少し入れたら塩味とコクがグッと上がるのでおすすめ✨️✨️
その時は塩控えめ
🦑 バーニャカウダソース
バーニャカウダーを造る時に混ぜる
アンチョビの代わりにする
🦑 イカと大根などの煮物
煮物ににいれるとイカ風味が増し凝縮した煮物に